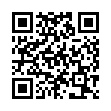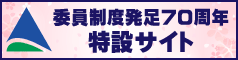足立区青少年委員会は青少年の健全育成に努めます!
活動報告
令和6・7年度 令和4・5年度 令和2・3年度 平成30年度・令和元年度 平成28・29年度
平成26・27年度
令和6・7年度 活動報告
事業部 研修部 広報部 ブロック共通 第1B 第2B 第3B 第4B 第5B 第6B 第7B
第8B 第9B 第10B 第11B 第12B 第13B その他活動
2024年11月1日
〔足立区社会福祉協議会へ〕
あだち区民まつりA-Festa2024に出展し、「1円玉アート」では事業部が作成した作品に善意の1円玉が多数投入されました。また、募金箱も設置し多くの方にご寄付をいただきました。2日間で集まった全額(¥45,418)を足立区社会福祉協議会に寄付をさせていただきました。
この「1円玉アート」は、今年も足立区のキャラクターを使用させていただき、図柄を完成する為に1円玉を投入していく仕様で募金活動を行いました。



2024年10月12日・13日
〔あだち区民まつり〕
荒川河川敷(虹の広場)にて、あだち区民まつり「A-Festa 2024」が開催されました。
青少年委員会では、ウォーターコイン・1円玉アート・ミニSLを出展いたしました。ミニSLは大人も乗ることができ、親子で楽しめ大人気です。10月に入ったとはいえ、今年はとても暑く大変でしたが、子供たちの楽しんでいる姿・笑顔に癒され、無事に終えることができ嬉しく思います。皆さまにご協力いただき本当にありがとうございました。





2024年6月27日 〜 7月7日
〔七夕飾り展示〕
区役所アトリウムにて「七夕飾り」の展示を行いました。
今年度は予想以上の短冊の数で(約1400枚)、笹が柳のように垂れ、大変盛況に終えることができました。皆さまが書いてくださった短冊は、西新井大師に納めさせていただきました。ありがとうございました。
『皆さまの願いが叶いますように』

2024年6月2日
〔青少年健全育成団体親睦ビーチボールバレー大会〕
第27回青少年健全育成団体親睦ソフトボール大会(平野グランド)を予定していましたが、雨天予報のため中止とし、第四中学校体育館にて「ビーチボールバレー大会」を開催しました。
親睦と言いながら、すべて真っ向勝負の激戦を制して小学校PTA連合会チームが優勝カップを手にしました。
ソフトボールはできませんでしたが、試合後の爽やかな笑顔の握手にこそ開催の意義があり、充実した1日を過ごせたと思います。ご参加の皆様お疲れ様でした。
大会結果
優勝 小学校PTA連合会チーム
第2位 スポーツ推進委員会チーム
第3位 小学校校長会チーム
第4位 青少年委員会チーム


2025年9月6日、7日
〔魚沼宿泊研修会〕
今期の宿泊研修会は足立区の子供たちが 中学になって体験する『新潟県魚沼』に決定した際、さてどのようなプランにするか?と悩みました。知っておきたい情報を収集し部会、魚沼観光協会のコーディネーターさん、旅行会社のコーディネーターさんと何度となく打合せを繰り返し調整してまいりました。 子供たちが、魚沼でどんな体験・経験をしているのかを私たち青少年委員が、身をもって体験・経験をする事が望ましいと考えプランを立て、実行することができました。 子供たちが宿泊する数々の宿舎の見学、笹だんごづくり、米詰め体験、そして大事な米作りの下折立・田圃の視察等とても充実した研修になったかと思います。 また、観光協会コーディネーターさんの足立の子供たちへの熱い思いを知り、子供たちは、魚沼でも見守られていることを知り、安心して子供たちを送り出せる環境に感謝の気持ちでいっぱいになりました。 バスでの移動中や懇親会等にて、ブロックの垣根を越えて懇親を深められたことも、大きな成果となっているかと思います。 この研修を経て、青少年委員が各校に出向いたとき『新潟県魚沼』について共通認識し、学校との連携に役立ていただけることを期待します。 最後に、ご協力いただいた魚沼観光協会の方々はじめご尽力いただいた皆様に感謝申し上げます。 参加いただいた皆さんの感想は委員専用ページの研修部アンケートからご覧ください。



2025年5月19日
〔フォローアップ研修会〕
前回の全体研修会『より良い関係づくりのためのコミュニケーションのコツ』を踏まえ、更にステップアップとして弁護士 遠藤啓之様をお招きし『世のトラブルはハラスメントにあり』をテーマにハラスメントについてのご講話をいただきました。 コミュニケーションの大切さ、人との関わり方、伝えることの難しさをこれまで以上に学ぶ機会になったのではないでしょうか。 第2部として、先生からの事例演習について各々の活動についての意見をグループディスカッションし、充実した時間を過ごしました。 委員の方にはアンケート結果、遠藤先生の事例演習及び模範回答を委員専用ページの研修部アンケートに掲載していますのでご覧ください。


2024年1月26日
〔全体研修〕『よりよい関係づくりのためのコミュニケーションのコツ』
全体研修の目的
影響を与える行動力や考え方を理解し、よりよい関係性を築くコツを知る。
また、青少年委員の活動に生かす。
1. コミュニケーションの基礎的な理解
2. 「あいさつ」と「呼び方」
3. うまくいく関係とうまくいかない関係
4. より良い関係づくりのために
講師 東京未来大学 日向野 智子 先生
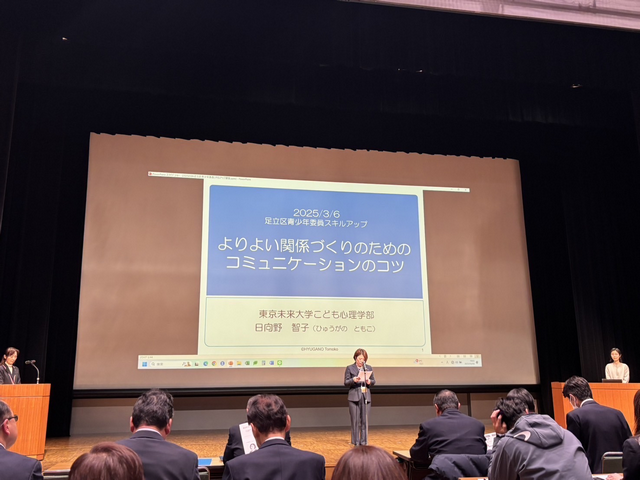
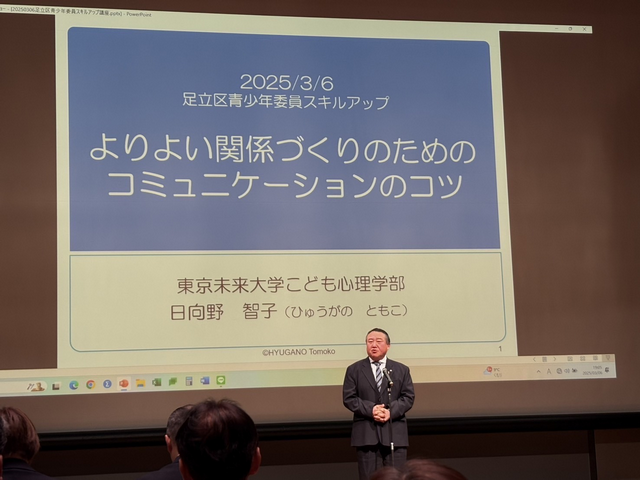

研修後のアンケート結果には、Iメッセージについてのコメントが多く
みられた。また、先生の講話から「言葉による伝達の限界と言葉以外の大切さ」を
改めて学んだ研修となった。
2024年11月17日
〔日帰り研修〕
鋸南自然の家、道の駅保田小学校、君津市の和蔵(わくら)酒造を訪れる日帰り研修を実施しました。鋸南自然の家では、児童が利用する施設を見学することで、自然教室の活動内容を具体的に理解いただけるよう企画しました。アンケートでは多くの好評をいただき、喜ばしく感じる一方で、スケジュールの改善を求める声もありました。内容の充実と時間配分の調整は引き続き検討が必要と感じています。参加者の皆さまに心より感謝申し上げます。
参加頂いた皆さんの感想は 委員専用ページ の研修部アンケートからご覧ください。


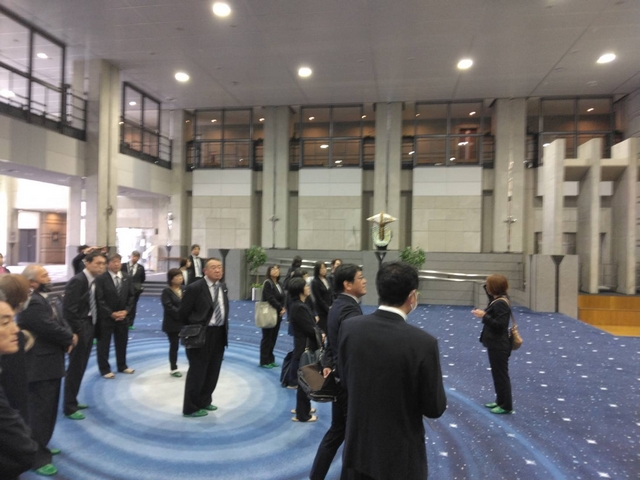
2024年7月11日
〔新任研修〕
第1部では学校運営部長を講師に迎え、「青少年委員の役割」についてご講話いただき、組織改正後の活動方針や地域との関わり方を学びました。第2部のグループディスカッションでは、新任と継続委員が様々な意見交換を行い、充実した時間となりました。アンケート感想では「目標が明確になった」や「内容の密度や時間配分に改善の余地がある」といった意見を頂きました。次回研修も、参加者皆様のニーズに応える企画を目指します。
参加頂いた皆さんの感想は 委員専用ページ の研修部アンケートからご覧ください。


2025年7月23日
東綾瀬にあるザ・イエローハウスにおじゃましました。この施設には公認心理師、保育士、臨床心理士、英語・韓国語が話せるスタッフが在籍し、未就学で発達の不安や、偏りのあるお子さんへの児童発達支援や、通園・通学中の集団生活で不適応の状態にあるお子さんが通う施設への保育所等訪問支援をされています。
発達支援では、専門職員が一人ひとりに合わせたプログラムで週1回1時間の「好きなあそび」から、関心・発展・発達へと導きます。発達支援に悩める親御さんにとって嬉しいサポートだと感じました。そして、訪問支援では、職員~子供~保護者のそれぞれの間に信頼関係が薄いと感じられる事が多くあるそうです。
問題行動を繰り返していると、𠮟られてばかりで疎遠になりがち。でも、「今日はちゃんと座っていられるね」など、優しい声掛けがキッカケで好転するとも伺い、信頼関係に大切な「誠実に共感しあえること」が出来ているかと自問し、反省満載な取材となりました。
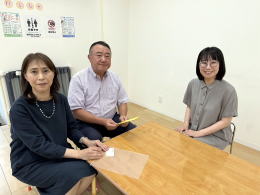

2025年5月17日〔けんちゃんの朝顔種まき会〕
六町駅前のロクマルステーションで行われた『けんちゃんの朝顔』種まき会に取材に伺いました。
足立区内で当時小1で交通事故で亡くなったけんちゃんが残した朝顔の種をお母さんの香さんが、交通安全のシンボルとなるよう願いを込めて配る活動をしています。
当日はあいにくの雨模様でしたが、香さんや、近藤区長から手渡された朝顔の種を、お父さん、お母さんに連れられた多くの子供たちが、一粒一粒丁寧に植えていました。交通安全の願いを広めたいと思いました。


2024年10月10日
文教大学東京あだちキャンパスに「100円朝食」の取材に伺いました。
学生が朝から食事を手軽にしっかり摂れるよう、大学関係者の助成もあり実施されていると担当の方より丁寧に説明していただきました。平日の朝、毎日提供することで食堂の方と学生さんが顔馴染みとなり、アットホームな雰囲気がとてもよかったです。朝食の重要性を再認識させていただきました。


2025年6月8日〔第28回青少年健全育成団体親睦球技大会〕
今年度は競技種目を「ビーチボールバレー」とし、東綾瀬中学校にて、青少年委員会主催の親睦球技大会を開催しました。
各団体2~4チームのエントリーがあり20チームが熱戦を繰り広げ、選手の掛け声、応援団の熱い声援で大変盛り上がりました。
会場を足立区勤労福祉会館プルミエに移し160人余りの参加者の中、成績発表、表彰式、そして各団体の紹介を行い、それぞれが親交を深め親睦球技大会は閉幕となりました。
ご協力いただいた皆さまに感謝申し上げ、来年の大会にも多くの方が参加されることを願っております。
大会結果
優 勝 スポーツ推進委員会
準優勝 青少年委員会
第3位 教育委員会
敢闘賞 小学校長会





2024年12月6日
各ブロックの令和6年度教育懇談会記録はこちら
2025年6月19日〔教育懇談会〕
楽しみながら学ぶ防災教育~防災カードゲームワークショップ~を千寿本町小学校にて行いました。昨年度に引き続き防災をテーマとし、アールシーソリューション株式会社 防災士・危機管理アドバイザーの大本 凛氏を講師として招き、防災教育に関する講演及び防災カードゲームを用いたワークショップを実施しました。
講演では、現在の防災教育の現状と課題について説明があり、防災教育にゲーム、アニメ、体験学習などのエンターテインメント要素を取り入れる意義についても紹介されました。
その後、防災カードゲーム「PREP(プレップ)」の概要説明とルール説明が行われ、4~5名のグループに分かれ、大本氏の進行のもとでプレイし、楽しみながら防災について学ぶことを体験し、プレイ中は参加者間のコミュニケーションも活発に行われ、親睦が深まりました。


2024年6月20日〔教育懇談会〕
今を大事に生きること、人と人の繋がりを大事にしたいと思い、第1ブロック・第2ブロック合同で『災害について考える』をテーマに講演会形式の教育懇談会を東京芸術センターにて開催しました。
平成23年に東京都被災地派遣教員として宮城県に赴任された矢部直意(足立区立第一中学校前校長)先生を講師にお迎えして、津波が中学校に押し寄せる映像や、生徒たちの避難誘導にあたった体験談や避難生活の様子などを知ることができ、地震、豪雨災害の多いこの国で改めて『防災意識を高める事』の重要性を学ばせていただきました。そして、この震災で日本だけでなく世界各国から思いやりの気持ちや物資など多くの支援が届けられた事も知り『地域・人との繋がり』の大切さを再認識しました。
今を生きる子供たちにどのように繋ぎ、生かされた命の大切さを伝えていけるかを考えていきたいと思います。

2025年6月24日〔教育懇談会〕
江北桜中ランチルームにて「不登校の現状と対応」をテーマの教育懇談会を開催いたしました。
各学校、日頃の子供たちの様子をはじめ不登校の現状と対応について校長先生よりお話を伺いました。
各学校共に不登校の子供たちが居て担任の先生はじめ養護教員、スクールカウンセラーやソーシャルワーカーの方々が子供たちの話を聞いたり家庭訪問をしたりとアプローチして、繋がりを切らない事が大切であり、毎週会議をしたりと学校全体で対応しているとの事でした。
子供たちも悩みや境遇がそれぞれ違うのでそこが大変とのお話も出ました。
改めて先生方のご苦労がわかる会になりました。
青少年委員に何が出来るのか考えていきたいと思います。


2024年6月20日〔教育懇談会〕
今を大事に生きること、人と人との繋がりを大事にしたいと言う思いから第1ブロック・第2ブロック合同で「災害について考える」をテーマに東京芸術センターにて開催いたしました。
平成23年に東京都被災地派遣教員として東日本大震災支援のため宮城県へ赴任された矢部直意(足立区立第一中学校前校長)先生を講師にお迎えして、改めて「防災意識を高める事」の重要性を学ばせていただきました。


2025年7月4日〔教育懇談会〕
「足立区子どもの貧困対策について」の講演と、「各校の近況報告」をテーマとして西新井住区センターで開催しました。
前半に教育委員会青少年課の西島課長より、貧困対策についての講演をしていただきました。足立区としての対策や地域の状況の説明、主要課題について特に貧困の連鎖が根底の課題となっているということ。子供たちへの様々な取り組みや支援をしていく中で、青少年委員の皆さまを通して地域の方々にも情報をお届けできるようご協力をいただけたらありがたいとのお話もありました。
後半は会食を兼ねての懇談会で、各校の近況報告をしていただきました。
講演や、ブロック各校の様子など情報共有しながらの和やかな実りある懇談会となりました。
2024年7月5日〔教育懇談会〕
「各校の現況と報告」をテーマとして西新井住区センター2F会議室で開催しました。
各校長先生より自校の1年間大切にしていきたいことや学校の特色等についてお話していただきました。
具体的には「伝えることを大切に」・「ICTと健康教育」・「伝統の継承と発展」・「校長室の開放(不登校や登校渋りを支える取り組み)」・「体験学習を多く取り入れよう」・「生徒一人ひとりが主人公」・「ICTと防災教育」等、これら各校の大切にしていることについて、具体的エピソードを交えてお話をいただいたことで、各校児童・生徒の輝いている日常を確認することができました。
今年度は、会食を兼ねての懇談会としたことで、終始和やかな中で会が進行しました。


2025年7月7日〔教育懇談会〕
「足立区の学校ICT教育の現状やこれからの方向性」をテーマに、前栗原小学校長であり、現在は学校ICT推進課・教育DXアドバイザーを務めておられる田中泰徳先生にご講話を いただきました。多くの情報の中から、ICT 環境のデータやデジタル技術を活用した教育の根本的な変革について、分かりやすくお話しいただきました。これからの社会で求められる資質・能力として、「やらされ感」ではなく、学ぶことへの興味・関心を持ち、自ら調整しながら他者と協力し試行錯誤して理解を深める学びの姿が重要であると説かれました。また、多様性のある学級の中で、一人ひとりに合った学び方を支援するためにICTが果たす役割についてもお話がありました。すべての学校が「第三ステージ」を目指し、アナログ の良さも取り入れつつ、今後100億円規模の予算を投じて、端末の更新やWi-Fi環境の整 備など、学習環境をさらに充実させていくとのことです。 講話の最後には、当日の内容を振り返る「復習クイズ」が行われ、子供たちが日々体験しているデジタルの世界を、実際に体験する時間も設けられました。


2024年7月1日〔教育懇談会〕
「人を活かし、困難を希望に変える」をテーマに、元足立区教育長でもあり現在は東京みらい中学校校長の定野司様より講話を頂戴しました。令和6年4月に開校した「東京みらい中学校」の校舎内外の写真を見ながら学校紹介をしていただき、学校に通う事が困難な生徒の新たな学びの場として「学びの多様化学校」の枠組みと特徴を活かした中学校を設置する事で不登校という教育課題、社会問題に対して取り組んでいると伺いました。
不登校の子を持つ保護者だけでなく、関係者全てに不登校を理解してもらうことが大事で不登校になってからの対策も重要だが、不登校になる前の未然の対策も大事であると思いました。前触れもなく突然不登校になるとの話に、不登校になっても動揺しないように知識を持っておく事の大切さも学びました。


2025年7月3日〔教育懇談会〕
足立小学校ランチルームに「子供たちと笑顔あふれる地域を目指して!」をテーマに学校・保護者・地域の代表者が集いました。
議題「育ちと教育の中で失ってはいけないモノ」では、PTAがボランティア制の保護者の会に変わり、中学校ではボランティア部が廃部に…等々「担い手不足」が多く聞かれ、引継ぎ・コミュニケーション・人の話しを聞く・日本の伝統文化・考える力・親子の関係・地域の関係などの回答に表れているようです。
しかし、名称は変わっても保護者が出来る範囲で学校を支え、有志の中学生ボランティアも活躍しています。本当に失ってはいけないモノは、時代の現状に合ったスタイルに変わりながら引継がれていくのではないかと感じられました。


2024年7月10日〔教育懇談会〕
「コミュニケーションでつなげよう、子供たちの未来!」をテーマに足立小学校ランチルームで開催されました。今年から開かれた学校づくり協議会会長も参加いただき、学校・保護者・地域の対話を深めることができました。
コロナ禍での活動自粛、黙食や、多国籍の生徒が増加するなど多様化する中で孤立している人も多く、解決に必要なコミュニケーション力を高める施策を伺いました。
コミュニケーションで大切なことは《主体は相手・五感で行なう・始めは発信から》や《おひたし》(怒らない・否定しない・助ける・指示は具体的に)など教示いただきながら、原点は《先ずは笑顔で相手の目を見て元気に挨拶ができる大人》がいることではないか、ということでした。
給食は過半数が小声会話を認める「緩和」になっているようですが、「前向き給食」は食事に集中でき時間内の完食率が増加している、食べる所を見られるのが恥ずかしい生徒もいる等の面も加味して対処が求められているようでした。


2025年7月2日〔教育懇談会〕
「これからの青少年委員のあり方」をテーマに、綾瀬小学校ホールにて教育懇談会を開催しました。 懇談会では、まず高橋青少年委員会会長から、テーマである、「これからの青少年委員のあり方」に関する講話がありました。その後、各校の校長先生、副校長先生、PTA会長、各青少年委員を交え、青少年委員の活動や期待される役割についてディスカッションが行われました。青少年委員が各学校関係者と情報交換しながら活動していくことの大切さを改めて確認できる有意義な時間となりました


2024年7月18日〔教育懇談会〕
「12年振りの生徒指導提要の改定に伴う教育現場の変化」をテーマに、土肥教育委員、各校校長先生、副校長先生、PTA会長を招いて、長門小学校体育館にて教育懇談会を開催しました。 懇談会では、校長先生お二方から、テーマである生徒指導提要に関する講話をいただいた後、各校PTA会長代表、青少年委員代表から、それぞれの所見を発表。さらに土肥教育委員から総評をいただく形で進みました。各関係者と情報交換しながら活動していくことの大切さを改めて確認できる有意義な時間となりました。


2025年7月3日〔教育懇談会〕
「部活動の地域連携」について 〜地域として何ができるか〜 をテーマに第十三中学校体育館にて、第7ブロック内の小中学校8つのグループに分かれテーマについて、グループディスカッションを行いました。
部活動が減少している中どうやって増やしていくのか又その対策について活発な意見交換ができ、学校ごとの思い・熱意を感じることができました。
今後も学校と地域と連携し、生徒の健やかな成長を支えていきたいと思う有意義な時間となりました。


2024年7月4日〔教育懇談会〕
「学校と地域を愛する心をどう育むか」をテーマに中川北小学校体育館にて、教育懇談会を開催いたしました。
学校ごとにテーマについて話し合いを行い、各学校で話をまとめて発表しました。活発なご意見が飛び交い学校ごとに子供たちへの思い、悩みなど色んな考えがある事を知りました。
その後の質疑応答でも、活発な意見交換がされ、地域との関係や青少年委員の役割等とても重要な事を改めて考えさせられました。
また、とても和やかな雰囲気で有意義な時間を過ごすことができました。


2025年7月10日〔教育懇談会〕
栗島住区センターにおいて、講師にユニバーサルスポーツクラブ「ゆにすぽキッズ」代表 神保有花様をお迎えし、学校と地域で育む『共生社会』~子供たちが生き生きと輝くコミュニティづくり~をテーマにご講演いただきました。
インクルーシブ教育は、障害のある子供とない子供とが共に活動することで社会性を養い、豊かな人間性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となりますが、学校教育の中だけで障害のある子供の将来の自立と社会参加に向けた指導をするのには限界があるのが現実です。
ゆにすぽキッズは、地域だからこそできることに着目し、ボッチャの練習会や大会を通して、子供たちが自信や達成感を得られて安心して活動できる場を提供しています。地域として活動することは、年齢・障害を越えた共生の場がつくりやすく、継続的な関係づくりが可能で、「自分も地域の一員」としての社会参加を見据えた活動を行うことができます。
その後、ボッチャ体験として、6チームに分かれて試合を行いました。ボッチャは初めてという参加者もいらっしゃいましたが、簡単なルール説明により、皆すぐに試合を楽しむことができました。
各コートでは好プレイ・珍プレイ(?)が連発し、拍手と笑いがあちこちで起こり、ブロック内の親睦も深めることができました。

2024年7月18日〔教育懇談会〕
「『地域と学校の連携』~部活動における新たな指導体制~」をテーマに勤労福祉会館にて教育懇談会を開催しました。
公益財団法人音楽文化創造より講師をお招きし、令和5年度文化庁文化部活動改革を受けて行った、部活動の地域移行に向けた委託実証事業参加団体のケースについてお話しいただき、その後、参加中学校より部活動の現状について報告をいただきました。既に部活指導員を導入している学校、地域移行の勉強会に参加している学校、地域から連携オファーがある学校と、それぞれ問題解決に取り組んでおり、今後も地域との連携を深めていくという意識を共有しました。


2025年6月12日〔教育懇談会〕
「子育て世代が知っておきたい介護保険、認知症、フレイル予防の情報、学校・PTAと地域包括支援センターとの連携」をテーマに、地域の関連団体をお呼びして桜花亭にて開催いたしました。
地域支援センター 一ツ家の方に活動の内容や介護、認知症等について、お話していただきました。今回の講話で、足立区の福祉事業や地域包括支援センターについて、初めて聞いた方が多くいらしたようです。子育て世代でも、これから起こりうる身内の介護や認知症、またフレイル予防について考える貴重な時間となりました。


2024年6月27日〔教育懇談会〕
地域の関連団体をお呼びして桜花亭にて教育懇談会を開催しました。
第1部は、今年度も『「地域の架け橋」青少年委員』をテーマとして青少年委員の役割や活動について物江青少年課長から講話をいただきました。更に第9ブロックの活動等の説明をし、参加された皆様に今後の活動の理解を得られたと思います。
第2部は、各校の学校紹介や情報交換を行った事で、今年度青少年課組織改正の目的である学校と青少年委員と開かれた学校づくり協議会・PTAの結びつきを強められる良い機会となりました。


2025年7月11日〔教育懇談会〕
竹の塚教育センターにて、Go!Go!!市民防犯推進プロジェクト市民防犯インストラクターの武田信彦講師をお招きし、「みんなで学ぶ子供たちと地域の安全」をテーマに教育懇談会を開催しました。
地域、大人(保護者)、子供のちからが合わさって子供たちを守ることができる。笑顔と挨拶は見守り、助け合いにつながり、人との関わりの中の防犯が大切であることを教えていただきました。
後半の実技では子供たちの防犯能力を引き出すコツとして、人との安全な距離の保ち方、SOSを発信し逃げる方法など説明していただき参加者全員で体験をしました。
「あいさつの種まきで見守りの花を咲かせましょう」とのお言葉が印象深く心に残り、今後も学校・地域と連携を深め、子供たちが安心安全に過ごせる地域を作っていきたいと思いました。


2024年7月19日〔教育懇談会〕
竹の塚地域学習センターにて、「地域との連携で絆を深めよう~青少年委員とは~」をテーマに物江青少年課課長による講演会を開催しました。貧困の連鎖が健康・治安・学力へ影響しているリアルな「足立区の子供を取り巻く現状」を説明していただき、長年の実態調査を挙げられ改善している項目もあると大変興味深いお話を伺いました。
青少年委員の位置づけとしては、行政・学校・地域のコーディネーター(連絡調整役)として、また、新たな青少年リーダーの育成や地域活動の応援、相談を行っているので、様々な団体と関わりのある青少年委員を活用していただきたいとお話がありました。講演後には各学校長に、子供たちの様子や取り組んでいることなど紹介していただき、先生方の「学校愛」を感じられた懇談会となりました。


2025年7月18日〔教育懇談会〕
昨年に続き、増え続ける不登校対策を地域で考えるために、東京都教職員研修センター教授である加藤明様の「地域と学校で出来る支援と共育」という講義を各学校・町会・自治会役員の方々を招いて開催いたしました。
不登校対策は学校だけでなく、地域の力も必要な為、今回は地域イベントを多数行っている町会・自治会の役員の方々にも参加いただきご意見などを伺いました。
地域イベントに沢山の子供たちが来ることで、地域に子供たちの居場所を作れたらと考えています。
これを機に学校と町会・自治会のコミュニケーションがより深まるように青少年委員としても活動していければと考えます。


2024年7月11日〔教育懇談会〕
「子ども達の悩みについて、不登校について考える」をテーマに第十四中学校第二会議室にて開催しました。不登校は、学校だけではなく地域全体の課題であることから、不登校を減らす為に学校と地域が協力できる事を模索する為、デリケートなテーマですがあえて取り上げました。
ディスカッションを活発にする為、事前に各学校長に実態調査のアンケートを取らせていただき、懇談会では、そのアンケート集計と独自に仕入れた保護者の声などを説明し、地域の現状を理解した上で各学校より意見をいただきました。
不登校のきっかけは多岐にわたります。その為対応策も多岐になります。唯一共通な対策は居場所づくりという点です。
学校や家庭以外の居場所としては、地域があり、イベントなどに参加する事で子供たちのレジリエンスも向上するという効果が実証されていますので、まずは学校と連携を深め地域の子供たちが不登校にならない様にできればと思います。


2025年9月27日〔鹿浜すこやかネットワーク〕
今年も恒例行事として青少年委員会第12ブロックが主催する「第29回鹿浜すこやかネットワーク」を鹿浜未来小学校体育館にて開催いたしました。今年は『 今誓う ~未来の自分へ~ 』をテーマに、各校を代表する小学生4名、中学生4名(計8名)に、未来の自分への応援メッセージや誓いを発表していただきました。
すでに夢の実現へ今から取り組んでいる子、これからじっくりと夢を決めていきたい子など、自分の想いを、緊張しながらも堂々と伝えられた素晴らしい発表会でした。
最後に、中村教育長から『自分の経験や体験を織り交ぜながら説得力のある表現でした』との講評をいただきました。伝統のある鹿浜すこやかネットワークも来年は第30回と節目を迎えます。より一層、すこやかな青少年育成の場となるよう努力してまいります。




2025年7月12日〔教育懇談会〕
「学力だけじゃない『非認知能力』を育む取組み」をテーマとして、ギャラクシティで開催しました。
本会の開催にあたり、各校の校長先生には、事前に “非認知能力を育むための取組内容”を、ヒアリングシートへ記入していただき、本会の協議用資料として冊子化し、参加者全員へ配付して議論いたしました。
本会の “プログラム1” では、各校の校長先生を代表して、皿沼小学校の加藤雅弘校長からプレゼンテーションを行っていただき、次に行われた “プログラム2” のグループディスカッションでは、校長・副校長・PTA会長・青少年委員の4つのグループに分かれ、役職や担う役割の違った観点から、非認知能力の向上策について議論し、最後に、グループの代表者から、各グループのディスカッション内容を発表していただきました。




2024年12月13日〔養護教諭との懇談会〕
毎年恒例となっております「養護教諭との懇談会」を青少年課 物江課長、青少年委員会 高𣘺会長、新田学園小学部 白石副校長をお招きし、新田学園第一校舎新田ルームにて開催いたしました。
各校の養護教諭からは、視力や虫歯などの受診率向上へ向けた取り組みや課題、保健室の利用理由には学年別の違いがあることなどの、大変貴重なお話しをたくさん伺いました。
また、各校の抱える不登校問題についての対策として、登校サポーターの紹介など、地域コーディネーターである我々青少年委員への期待や要望等についても話し合いが行われました。
今回の会を通じて、各校のそれぞれの課題が共有でき、今後の青少年委員としての活動への決意をあらたにした有意義な懇談会となりました。




2024年9月28日〔鹿浜すこやかネットワーク〕
毎年の恒例行事となっている「第28回 鹿浜すこやかネットワーク」が、鹿浜第一小学校体育館にて開催されました。今年は『ありがとうの花を咲かせよう~見つけよう・伝えよう』を共通テーマとして、各校を代表する小学生4名、中学生4名(計8名)から、ありがとうの持つ力や、いつも助けてくれる両親や尊敬する方々への感謝の気持ちなどが発表されました。
鹿浜すこやかネットワークの目的は、児童生徒たちが自分の考えを整理して発表することにより、表現力やコミュニケーション能力を向上させ、自己肯定感や自信を育むことにありますが、最後に、中村明慶教育長からの講評もいただき、改めて、鹿浜すこやかネットワークの有意義さを感じさせられました。


2024年7月13日〔教育懇談会〕
「学校・PTA・青少年委員の連携体制を再考協議」をテーマとして西新井ギャラクシティにて開催し、各校の校長およびPTA会長の皆様に参加していただきました。
今年度のテーマの設定趣旨は、新型コロナウイルス感染症の流行により、学校行事・PTA行事の運営スタイルを余儀なく変えることとなりましたが、この苦境の経験を機に、学校・PTA・地域とのコーディネーター役である青少年委員においても、従来からの慣習に囚われず、学校・PTAとの連携体制を再考し、改善すべく見直しの転換期にあると思慮したためであります。
なお、本会の開催にあたり、校長・PTA会長の皆様から事前にご提出いただいた「教育懇談会ヒアリングシート」に基づき、各校の青少年委員との連携に関わる課題(As-Is)を整理のうえ、要望・期待事項等(To-Be)に対する改善方針案を検討させていただき、第12ブロック青少年委員が、地域とのコーディネーター役として、従来からの活動に加え、より一層の役務を果たすための改善方針(アクションプラン)を本会にて協議させていただきました。
[改善方針](アクションプラン)
①定期的な3者懇談会の開催
校長・PTA会長・青少年委員との3者が定期的(四半期に1回程度)に情報交換を行う機会を設け、学校・PTAの抱える課題を整理し、助言やサポート等を行う。
②必要時にPTA運営委員会へ参加
PTA運営の円滑化および再活性化を目的とし、必要時にはPTA運営委員会へ出席し、PTA活動に対する助言やサポート等を行う。


2025年6月12日〔教育懇談会〕
「地域を守る防災・防犯力〜ともに備え、ともに守ろう〜」をテーマに舎人小学校体育館にて開催いたしました。学校だけではなく地域全体の課題であり、天災について防ぐことは難しいが、避難の方法により被害を最小限にとどめることが出来るように各校の取り組みを発表していただきました。
今回の会を通じて、各校毎月防災・防犯に関する取り組みをしていることを伺い、日頃からの学ぶ機会を繰り返し行う重要性を学ばせていただきました。何時どこで起こるか分からない災害に対して、人と人との繋がりを大切にし、一日一日を大切に行動していきたいと改めて確認できる有意義な時間となりました。


2024年7月2日〔教育懇談会〕
『コロナ禍後の子どもたちの様子と不登校について』をテーマに学校ごとに発表していただき、その後、ディスカッションを行いました。
各学校のコロナ禍後の子供たちの様子を聞くと、小学校の方は子供たちの多くはマスクを外した生活になってきているが、中学校の方は思春期ということもあるのかほとんどの子供たちがマスクを外せない状況で対照的な現状がありました。
また、不登校についての現状や取り組みについても各学校から発表をいただきました。
とてもデリケートな課題でしたが、各校とも正面から課題に向き合い真摯に取り組まれていることが伝わる発表とディスカッションになりとても貴重で有意義な時間になりました。

2024年9月9日
〔近藤区長と青少年委員会役員で懇談会〕
各専門部部長より活動内容と各ブロック長からは地区対での活動および担当校の悩みや抱えている問題など多くの情報提示がされました。それに対して現状報告やアドバイスを近藤区長や中村教育長よりいただき、また、青少年委員会の活動を行政の広報紙に載せてはとの提案もありました。


2024年4月6日
〔足立区青少年委員会委嘱式〕
中村明慶(なかむら あきよし)教育長より、委員一人ひとりに委嘱状が手渡され、その後、髙𣘺將郎新会長が代表挨拶にて抱負と決意を述べられました。
また、委嘱式後には、臨時全体会と専門部会が開催され、一期2年間の青少年委員会活動がスタートしました。